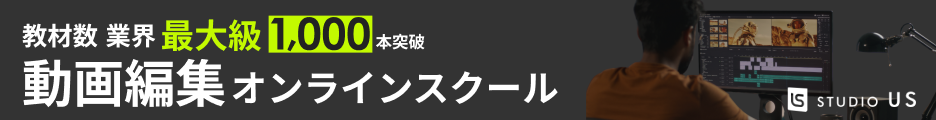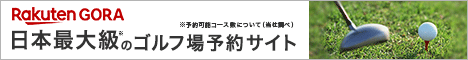今回は、前回のVol.13にてすべて説明を行うことが叶いませんでした「鳥居」についての解説をさせていただこうと考えております。
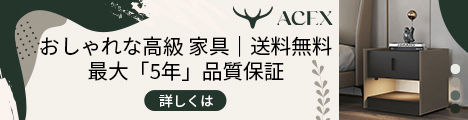
神社に入ってまず目に入るのが鳥居ですよね。神社における象徴的な存在ともいう事ができる鳥居にはどのような意味や種類があるのかをご説明させていただこうと考えております。
- 一の鳥居とは?
- 神社にとって「鳥居」とはどのような意味があるのか
- 鳥居の語源について
- 鳥居にはどのような種類があるのか
- 日本最大の鳥居
- 千本鳥居とはどのようなものか?
一の鳥居とは?

一般的な神社においては、鳥居は一つが基本です。
特に規模の大きな神社では、二つ以上の鳥居がある場合があります。境内の外側にある鳥居から一の鳥居・二の鳥居・三の鳥居と呼び、一の鳥居から順に鳥居をくぐり参道を通って社殿までたどり着くことが出来ます。通常、三の鳥居まであるのが一般的です。
・神社にとって「鳥居」とはどのような意味があるのか

鳥居は神域と俗世との境界を示し、神聖な神域を区切る役割があります。また、鳥居をくぐることで参拝者が悪い運気を払い、浄化させるとも言われています。
・鳥居の語源について

鳥居の語源について有力な3つの説をご紹介したいと思います。
一つは神様が「通り入る」という意味が転じた言葉という説です。
もう一説は、天照大御神にまつわる有名な日本神話である天岩戸の神話にて「常世の長鳴鳥」が止まった宿り木をルーツとする鶏居(鶏の止まり木)であるという説です。
もう一説にはインド仏教にみられる「トラナ」と呼ばれる門や海外の建築様式から起源を求める説があります。
・鳥居にはどのような種類があるのか
材質
木材で作られた「木鳥居」、石で作られた「石鳥居」、金属を用いた「金鳥居(かなどりい)」が存在します。



・鳥居の形式

日本でも最も知名度の高い「厳島神社」の大鳥居と同様に両部鳥居を使用しています。
名称にある両部とは密教の金胎両部(金剛・胎蔵)をいい、神仏習合を示す名残であると言われています。四脚鳥居などの別名があります。
鳥居には大きく分けて2種類の形式があり「神明鳥居」と「明神鳥居」があります。
神明鳥居(しんめいとりい)

最も一般的で歴史の古い鳥居。上の横柱がまっすぐで見た目も作りもシンプルな鳥居。横柱(笠木)に反りがなく一直線で、二段目の柱(貫)が支柱部分より突き出ていないことが特徴です。神明・天祖と呼ばれる天照大御神を御祭神とする神社は、ほとんどこの神明鳥居を使用していらっしゃいます。
明神鳥居(みょうじんとりい)

上の横柱(笠木)が天に向かって反っているのが特徴となる。柱も地面に対して少し傾斜をつけてたてられる。木造で朱塗りであるのが主流。ご祭神が天照大御神の系譜を辿っていないことが多くあります。
もう少し細かく分類すると神明(しんめい)・伊勢(いせ)・鹿島(かしま)・靖国(やすくに)明神(みょうじん)・両部(りょうぶ)・住吉(すみよし)・山王(さんのう)など様々な鳥居の種類が存在します。






・日本最大の鳥居

日本最大の鳥居
熊野本宮大社(和歌山県和歌山市)鉄筋コンクリート製・高さ33.9m・平成11年(1999年)建造。
日本で二番目に大きな鳥居
大神神社(奈良県桜井市)耐候性鋼板・高さ32.2m・昭和61年(1986年)建造。総重量180トンの耐候性鋼板で出来ており、1300年の耐久性があるとされ、マグニチュード10の地震にも耐えられる構造となっているといいます。
日本で三番目に大きな鳥居
弥彦神社(新潟県西蒲原郡弥彦村)耐候性特殊鋼製・高さ30.16m・昭和57年(1982年)建造。上越新幹線開通を記念して建造され、建造当初は日本一の大きさを誇っており、額束は畳12枚分にも及びます。

木造の鳥居としては日本最大を誇るとされます。

日本三大鳥居の一つに数えられ、日本で最も有名な鳥居と言っても過言ではありません。主柱には楠の自然木を使用し、控柱には杉を使用しています。
・千本鳥居とは?

京都の伏見稲荷大社をはじめとして、特に全国各地に存在する稲荷神社には幾重にも鳥居が連なっている「千本鳥居」が存在します。その千本鳥居には一体どのような意味があるのでしょうか。
1) なぜ鳥居が「数多く」連なっているのか
特に稲荷信仰では「商売繁盛」「家業繁栄」を願って企業や個人が鳥居を奉納した結果です。
鳥居奉納は「祈願と成就のしるし」として次々に新しい鳥居が加えられていきます。
2) どのような神社に見られるか
※千本鳥居が存在するのは「稲荷神社」であると考えていただいて構いません。
全国に3万社存在する稲荷神社の総本宮である伏見稲荷大社(京都)をはじめ、その他の稲荷系神社や地域の稲荷社、摂社や末社に存在します。
3) 色や構造・宗教的意味
赤(朱)は古来、火・太陽・生命を表し、魔除け・災厄払いの力があると考えられ、朱の塗料には防腐効果があり、木製の鳥居の保存にも都合が良く実用的であったようです。
鳥居が連続することで「神域へ入っていく道」が強調され、入る者の気持ちが整えられます。数多く置くことで「俗界→中間→聖域」といった多層的な区切りや、秘境感を演出する可能性があります。
※学術的には諸説あり、完全に定説化された説明は一つとは言えません。
いかがでしたでしょうか。今回は鳥居について詳しく解説いたしました。

次回は日本百景にも選出されているかの風光明媚な絶景を望むことができる有名な観光スポットへと参拝の旅を行います。日本一の名峰である富士山の山麓に抱かれる日本神話にも登場する有名な女性の神様をお迎えに上がります。
それでは次回、いざ絶景の旅に参ります!