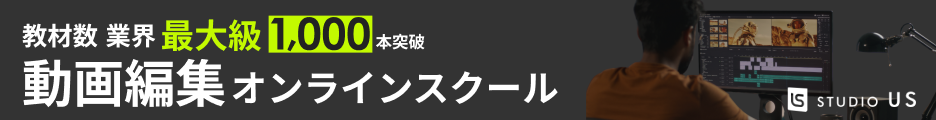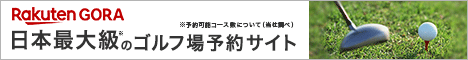今回は、参拝の作法その2と称して「鳥居のくぐり方と参道の歩き方」について皆さんにお伝えさせていただきたいと考えております。一般的には、神社の参拝をするための明確な作法や仕来たりが存在するのかどうかを教えていただく機会は滅多にありませんよね。
神社とは突然、街中や都会のビルの合間にも現れ、初詣や地域のお祭りなどで栄える大変身近な存在ですが、かたや太古の昔より日本の伝統文化を重んじる神聖かつ重要な地ですが、厳格な作法が存在するかどうかわからないことが多いと思います。
また、反対に全く仕来たりやルールなどを気にする必要はないのかどうか、参拝をしながら心許ない思いをされた方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか?
そこで今回は、鳥居のくぐり方と参道の歩き方に焦点を当てて皆様にお伝えしようと思います!

私個人の見解
今回は神社の作法についてお話をさせていただいておりますが、あまりにも神社の作法に気を使ってしまうがあまりに、神社の参拝そのものを楽しむことができなくなってしまうという不具合が生じてしまう事があります。
綺麗な朱塗りの鳥居だな、参道の両側に燈籠が立ち並んでいて玉砂利がまっすぐに敷き詰められている素敵な参道だな、と感じながら境内を歩くことに楽しみを感じる事があります。

神社の敷地内に伸びている木々にも様々な特徴があり、御本殿にお祀りされていらっしゃるご祭神の御心を表しているかのように空に向かってまっすぐに整然と伸び並んでいる参道や、雷鳴が轟く空の様な荒々しい様相で伸び栄えた樹木が立ち並んでいる参道もございます。
御神木の葉が重なり合う音や神社の社殿に用いる材木の香り、玉砂利を踏んだ際に足元で小石がこすれ合う感覚など、神社の境内にある様々な景観を五感で感じながら神社の参拝を行う事も楽しみ方の一つでございます。
今回の旅は、あまり難しく考えずに神社にお祀りされている神様への感謝の気持ちと敬意をお示しする方法の一つとして参考にしていただけると大変ありがたく思います。
それではいざ参拝の作法の旅に参ります…
鳥居のくぐり方と参道の歩き方
STEP.1 鳥居のくぐり方
STEP.2 鳥居への足の踏み入れ方
STEP.3 参道の歩き方
STEP.4 本殿から帰る際
STEP.5 帰る際の鳥居のくぐり方
STEP.1 鳥居のくぐり方

一.鳥居の前で立ち止まる
二.一礼する
三.鳥居をくぐる
注意点の一つとして、一礼を行うのは鳥居をくぐった後ではなく、鳥居をくぐる前に立ち止まって行ってください。
鳥居をくぐる際には鳥居の左側か、もしくは反対の右側からくぐることが正式な参拝方法と言われています。
参道を歩く際には、神社の参道の左右の端を歩くのが仕来たりであるといわれていることに由来しています。神社の参道の中央は「正中(せいちゅう)」と呼ばれており、神様が通るための道であると伝えられています。
参拝の作法に関して厳格な態度を求められる方は参道の左側を歩くことが正式な参拝方法であるとおっしゃる方もいらっしゃいます。
▶混雑時には…
正確には神社の参拝を行うための作法というわけではございませんが、初詣などで年末年始に神社が人で混雑している場合にスムーズに参拝を行う方法がございます。
それは①鳥居の左側から参道に入り②本殿にて参拝を終えた後に③左側から本殿を後にし④鳥居の左側から帰る。その様にすると、多くの参拝をされている方々と鉢合わせをせずに参拝を行うことができるというお話を伺いました。
もし興味がございましたら参考になさってください。
左側通行で統一するスムーズな人の流れができるという事ですね!
STEP.2 鳥居への足の踏み入れ方

・鳥居の左側から足を踏み入れる場合は「左足」から
・鳥居の右側から足を踏み入れる場合は「右足」から
どのようにして踏み入れる足が決まるのかというと、先ほどお伝えした「正中」が神様のお通りになる道であることから、踏み入れる足によって神社にお祀りされている神様に背やお尻を向ける事が失礼な態度に当たるためだと伺いました。
左足から足を踏み入れると自然と正中に体の正面を向ける態勢になりますよね。
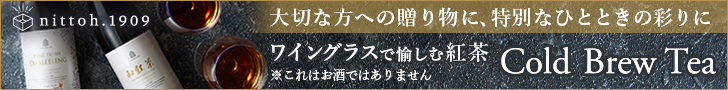
STEP.3 参道の歩き方

神社にも催事の際に、座席に用いる席次のように上位と下位があります。本殿まで続く、参道の中央である「正中」が最高位です。どうしても正中を横切らなければならない場合には一礼をするとよいそうです。
参拝している神社が指定している場合はそちらに従うとよいと伺いました。
鳥居を左側からくぐった場合は、そのまま参道の左側を進むとよいと思います。
玉砂利が敷き詰められている参道も数多く存在いたしますが、玉砂利を踏むことは心身を浄化させる効果があると伝えられています。
▶玉砂利を踏むことの効果
玉砂利の“玉”には「魂」や「御霊」という意味と、「玉のような」という表現でも使われる、美しさ・宝石・大切な物、という意があり、“砂利”とは本来はさざれ石のことを指し、ミタマの宿った、美しい宝石のような、小さい石ということになります。
そのような清らかな石を踏むことで、参拝者がしだいに身を清め、最高の状態で祈ることができるよう配慮されているのだそうです。
参道を歩く際に砂利を踏む音や感覚によって、参拝者は心を落ち着かせ、清浄な状態で祈りを捧げることができます。
STEP.4 本殿から帰る際

参拝を終えた後にご本殿から帰る際には、正中に向かって背を向けないように振り返るとよいと思います。内側を向きながら振り返るようにすると覚えていただくとよいと思います。
STEP.1でお伝えした様に、混雑時に人の流れが出きるのスムーズな参拝の仕方を実践する場合は、本殿で参拝を終えた後、正中に向かって背を向けないように内側を正面にしながら振り向き、ご本殿を背にして左側の道順を取ります。
※拝殿での礼や拝の作法については今後、別の回にてご説明いたします。
実際にご参拝をされる際には、ご本殿以外の社務所や安置されている遺物、御神木や宝物殿などその他にも拝見する箇所は数多く存在します。
それに加えて、広い境内を練り歩いている最中に、お手洗いをお借りする事もよくあることです。そのため、必ず参道の左側を通って参拝を終える事ができるとは限りません。
道順に気を取られすぎて見物をしたい箇所を見落とさないようにして下さい。(先ほども申しました通り、正中を横切る際には一礼をするとよいと思います)
STEP.5 帰る際の鳥居のくぐり方

鳥居を出る際には本殿へと向きなおして神様への感謝お気持ちや崇敬の念を示すために一礼を行うと神様もお喜びになると思います。
神社の外に出る際
一、鳥居をくぐる
二、内側を向いて振り返る
三、本殿へ向かって一礼
四、内側を向いて神社の外へ向き直る
振り返り方も、鳥居への足の踏み入れ方と同様に、神社の神様のお通りになる中央(正中)に体の正面を向けて行うとよいそうです。
鳥居をくぐった後に参拝を行った神社のご本殿へと向き直ります。本殿へ向かって心からの感謝の気持ちをもって一礼を行います。帰る方向に向き直って神社を後にします。
振り返る際には、すべて正中を意識しながら「内側に体を向けて振り返る」と覚えておくと理解しやすいと思います。
あくまでも習わしですので、必ずこちらでご紹介した作法を忠実に守らなければならないという事ではありません。
大切なことは神社への崇敬の念を忘れず、神社を守られていらっしゃった地域の方々へ感謝を行う事と同時に、神社へ参拝ができる事へ感謝を行う事であると思います。
※また「忌中」と言われる親族が亡くなってからの2カ月程度の期間は鳥居をくぐってはいけない期間であると伺いました。目安は五十日祭までの五十日間と言われています。
いかがでしたでしょうか?神社に到着した直後に面前に広がる、鳥居や参道への入り方の作法を詳細にお伝えいたしました。
正中を意識すると自然と足の踏み入れ方や振り向く方向が理解できますよね。実際に神社へ訪れた際には実践してみてください!

次回は仙台藩のお膝元である陸奥国一之宮へと参拝に参ります。日本で最も多い本マグロの年間水揚げ量を誇る塩釜漁港からほど近くに鎮座していらっしゃる神社です。
お祭りされていらっしゃる神様は、塩の精製をこの地に伝え、潮の満ち引きにも関わるという大変重要な役割を担っていらっしゃったと伺っております。さて、いったいどのような御神徳に与ることができるのでしょうか?
それでは次回、いざ東北の地へと参拝に参ります!