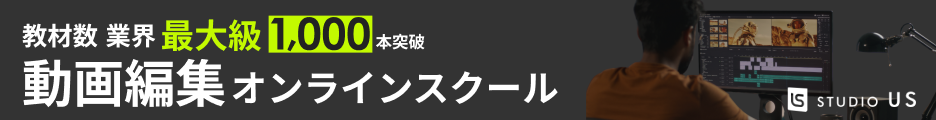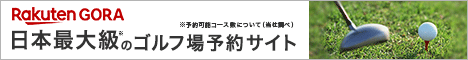前回ご紹介した鹿島神宮と香取神宮、息栖神社の三社を合わせて東国三社と呼ばれています。
これら三社の鎮座位置はその入り口にあたり、うち鹿島神宮・香取神宮は大和朝廷の東国開拓の拠点として機能したそうです。また、三社の位置は二等辺三角形を描くことが知られています。
江戸時代には「下三宮参り」と称して、関東以北の人々が伊勢神宮参拝後に三社を参拝する習慣がありました。
今回は、鹿島神宮から出発し、千葉県香取市に鎮座している東国三社の内の一社、香取神宮へ訪れてみたいと思います。鹿島神宮と同じく、地中で大暴れしている巨大ナマズの尾を抑えているもう一方の要石に今後、地震の被害が起こらないことを祈ろうと考えております。
皆さま、最後まで東国三社の旅の続きにお付き合いください!

今回のルート
S鹿島神宮を南下し1息栖神社へ向かう。利根川を越えて千葉県へ入ります。
香取市にあるお目当ての2香取神宮は目と鼻の先。三社を結んだ線は二等辺三角形を描くと言われています。
息栖神社

場 所:茨城県神栖市息栖
御祭神:久那戸神(くなどのかみ)
天乃鳥船神(あめのとりふねのかみ)ご由緒・ご祭神
久那戸神(くなどのかみ)は国譲りの際に武甕槌大神と経津主大神を先導したと言われる神様です。
主祭神である久那斗神は、厄除招福・交通守護の神であり、井戸の神でもあります。また相殿神である天乃鳥船神は交通守護に、住吉三神は海上守護にご神徳があります。
息栖神社本殿

鹿島神宮、香取神宮と比べるとそれほど広大な敷地な境内ではありませんが由緒ある神社の風格を感じます。
この季節は茅の輪くぐりができるようになっていて、この輪を三回順番にくぐると厄除けや健康祈願が出来ると言われています。

境内に面した鳥居から少し離れたところに「忍潮井(おしおい)」と呼ばれる2つの井戸があります。「男瓶」「女瓶」という名の2つの土器から水が湧き出ていて。
女瓶の水を男性が、男瓶の水を女性が飲むと二人は結ばれるという言い伝えがあり、縁結びのご利益もあるとされています。
▶忍潮井の伝説とは
息栖神社が日川から今の地に遷座した際に、取り残された男女の二つの瓶は神のあとを慕って三日三晩哭き続けたのだそうです。二つの瓶はとうとう自力で川を遡り、一の鳥居の下に据え付きました。この地に定着した後も、時々日川を恋しがり二つの瓶は泣いたという伝説があるそうです。

息栖神社の御朱印はこちらです。
神社のお名前が記されない比較的シンプルな御朱印ですね。
下総国一之宮 香取神宮

ご由緒・ご祭神
場 所:千葉県香取市香取1697
ご祭神:経津主大神(ふつぬしのおおかみ)香取神宮は古くから国家鎮護の神として皇室からの御崇敬が最も篤く、中世以降は下総国の一宮として篤く信仰されています。
現在は神宮との称号を拝されている神社は多く存在しますが、明治以前に『神宮』の称号を得ていたのは伊勢神宮・香取神宮・鹿島神宮の三社のみでした。
家内安全、産業(農業・商工業)指導の神、海上守護、心願成就、縁結、安産の神として深く信仰されています。さらに、その武徳は平和・外交の祖神として、勝運、交通 安全、災難除けの神としても有名です。※御神徳とはご利益の事です。
経津主大神とは…
鹿島神宮の御祭神である武甕槌大神(たけみかづちのおおかみ)と共に出雲大社のご祭神である大国主命(おおくにぬしのみこと)と話し合って国譲りの交渉を成就し、日本の建国を行った武神・軍神。
▶もっと詳しく
天照大神が葦原中国(現在の日本における地上世界の事ですね)で八百万神に相談すると、 経津主大神に加えて武甕槌大神も名乗り出る事となり、二神は共に出雲に派遣されることとなりました。
出雲国の稲佐の小汀 に辿り着いた経津主大神、武甕槌大神が十握剣(とつかのつるぎ)を抜き、逆さに突き立て武威を示すと、大国主神は天照大神の命令に従い葦原中国を譲りました。
二神は大国主神から平国の広矛(くにむけのひろほこ)を受け取り、日本の国を平定して、天照大神の元へ復命されました。
奈良の春日大社、宮城の鹽竈神社を始めとして、香取神宮のご祭神である経津主大神を御祭神とする神社は全国各地に及んでいます。広く尊崇を集めていらっしゃるそうです。
香取神宮の門前町

ようやく到着いたしました。今回の旅の最後の目的地である神社です。こちらに伺った頃にはすでに16時30分を過ぎており社務所で御朱印がいただけるかどうか心配です。
香取神宮一の鳥居

こちらが香取神宮の一の鳥居です。石の支柱に「香取神宮」と表記してあります。
必ずと言ってよいほど神社にある表札のような役割をしているこの石の支柱を「社号表」と呼びます。時々使用しますのでぜひ覚えておいてくださいね。
香取神宮の参道

玉砂利が敷き詰められている参道の両側に装飾の施された燈籠が立ち並んでいました。丁寧に手入れの行き届いた心地の良さを感じる参道でした。
参道とは…
神社の拝殿へ向かう道のことを指します。
神社の参道のうち、おもに正面に位置するもの「表参道」と呼び、脇道には地名や方角をつけた参道や裏参道と呼ばれるものもあります。表参道とは東京青山周辺のおしゃれな通りの名称なだけではなく、神社の参道のうち正面に位置するものをいうんですね。
東京青山の「表参道」とはもともと明治神宮の参道として整備された大通りがそのまま地名となったそうです。
香取神宮の神門

香取神宮の神門です。本殿のある広場に入る前にある門の事ですね。
香取神宮の建築物は手入れや改修が何度も行われているのでしょうか。非常に華美な装飾が施されていて綺麗です。
手水舎

手水で身を清めます。こちらを右に進むと本殿があるそうです。進んでみましょう。
香取神宮の拝殿

香取神宮の拝殿に到着いたしました。一般的には賽銭箱が設置してあり、参拝を行う場所を「拝殿」と呼びます。一方、その後方に位置する建屋を通常は「本殿」とお呼びいたします。
木造平屋建てで、檜皮葺。これだけ華美な装飾が施されている拝殿は珍しいですね。初めて訪れたことに対してご挨拶をし、お力をお貸しくださいと祈願いたします。
香取神宮の奥宮

先ほどの手水舎から本殿と反対側に進み5分ほど歩くとこちらの奥宮へと到着いたします。
多くの場合本殿が山の麓に位置しているのに対して、奥宮はその神社の鎮座する地の険しい山の中腹や山頂に鎮座していることが多いのです。鹿島と香取は境内の敷地内に奥宮があるというのが珍しいですね。

こちらでは香取神宮の奥宮の身でいただける御朱印もあり、社務所もこの近くにあります。参拝をさせていただきます。神妙な面持ちで2拝2拍手1拝を行います。
香取神宮の要石

大ナマズの頭を押さえているのが鹿島神宮の要石。大ナマズの尻尾を押さえつけているのが香取神宮の要石だそうです。

鹿島の要石は石の頭が凹んでおり、香取の要石は凸型であるそうです。地中で暴れて地震を起こすナマズを抑えているそうです。
新海誠監督の作品「すずめの戸締り」に登場する要石のモデルとなったのはおそらくこの石ですね。非常に壮大なスケールで描かれたアニメでした!もし興味がございましたらご覧になられてはいかがでしょうか。

こちらが香取神宮の御朱印です。
少し丸くてかわいらしい印象の文字の形をしています。
※詳しいアクセス情報やご由緒については🔗香取神宮の公式ホームページをご覧ください。
帰路のルートは香取神宮から栃木県宇都宮市街で寄り道をして福島の会津若松を通り、新潟へ戻ります。
おおよそ6時間で帰宅できる予定です。
宇都宮市街

考えていた以上に発達した都市であると感じました。完全に日が暮れた後に到着いたしましたが、ネオンや街灯が立ち並ぶ綺麗な街並みでした。
宇都宮屋台横丁

風情のある居酒屋が狭い路地に立ち並んでいます。
非常に楽しそうな雰囲気に気分も高揚いたします。こちらの写真を見ただけでもワクワクしますよね。
手作りぎょうざのふたあら

風の噂によるとこちらの店舗は現在、閉店してしまったとも伺いました。
こちらのお店の従業員の方に鹿島神宮への参拝後に新潟への帰路を目指している事をお話しさせていただき、とても気さくにお話を伺っていただきました。
餃子と一緒に麵料理を提供していただきました。

自家製のもちもちの皮で包んだ餃子の餡を、口の中に放り込むとジューシーな肉汁が溢れてきます。パリパリに焼いた餃子の皮が香ばしく、店主のお姉様自家製の特製ラー油をたっぷりのせて一気に食べ進めます。
食事も、店員の方々に対しても、非常に満足した時間を過ごさせていただきました。
これから帰宅の途に就こうと思います。
まとめ
香取神宮を出発してから程なく、ナビが故障してしまい、進路を見失いながら4時間ほどかけて栃木県宇都宮市へ到着しました。
実は、宇都宮から高速道路を利用したのですが職場の方へお配りするお土産は何にしようかと考えているうちにいつのまにかガソリンが尽きてしまいましたが、なんとガソリンスタンドのあるパーキングエリアまで到着できそうにありません!!
困り果てた挙句、自動車保険会社へ連絡をして応急処置としてガソリンを供給していただきなんとか帰宅することができました。結局新潟へ帰宅したのは朝の6時を過ぎており、大変恥ずかしい思いをいたしました。

ここまで長い間お付き合いいただきありがとうございました!
次回は長野県(旧国名:信濃国)にご鎮座されている、私自身の起源を探る神社の旅を皆さまにお伝えしたいと考えております。
皆さま次回の旅のご準備をお願いいたします。それではいざ次回の旅へと参ります!